神戸の西区にある、紅茶専門店アリエル。
砂糖をいれて飲もうとすれば「緑茶を飲むときでも砂糖をいれるのですか?」なんて、マスターから言われてしまうお店です(笑) でもなるほど、その話を聞いていると、色々と納得させられることが多々。美味しい紅茶を飲んでもらいたいという、その想いがよく伝わってきます。お店のホームページによると、紅茶の効能には以下のようなものがあるそうです。
・カテキンが皮下脂肪をエネルギーに変えるので肥満の防止になる。(ダイエット効果)
・カテキンが風邪のウイルスの働きを抑制する。
・カテキンが虫歯を撃退し、予防してくれる。
・カフェインやカテキンが胃液の分泌を促す。(食欲増進作用)
・赤痢菌・コレラ菌・腸炎ビブリオなどの病原菌を撃退する。
・カフェインは新陳代謝をよくして、利尿作用を促す。
・カフェインが中枢神経を刺激し、眠気を取る。(覚醒作用)引用元:紅茶のお話し
さて、今日はそんなお店を評するときによく使われる、「こだわり」「こだわる」という言葉について考えてみたいと思います。
「こだわり」や「こだわる」の本来の意味について
辞書サイトから、「こだわる」の意味を引用してみます。
1 ちょっとしたことを必要以上に気にする。気持ちがとらわれる。拘泥(こうでい)する。「些細(ささい)なミスに―・る」「形式に―・る」
2 つかえたりひっかかったりする。
「それ程―・らずに、するすると私の咽喉を滑り越したものだろうか」〈漱石・硝子戸の中〉
3 難癖をつける。けちをつける。
「郡司師高―・って埒(らち)明けず」〈浄・娥歌かるた〉
「こだわる」とは、ささいなことを必要以上に気にすること・気にしなくてもいいことを気にすることが元々の意味だったんですね。つまり、悪い意味を表します。「そんなことを気にするだなんて、小さい人間だなぁ」というようなニュアンスですね。関西弁でいうと「自分、気にしいやなぁ」になりますか。
「こだわり」というのは、すべてを見ることが出来ないというのが原義。元々否定的な言葉なので、「こだわりがある」というのは実は表現としてはおかしいのです。
「こだわり」の変遷 …言葉って変化するものだから
「こだわりのあるお店」「素材にこだわったお店」など、最近では「こだわり」「こだわる」という言葉も肯定的な意味で使われる(誤用される)ことが増えてきました。言葉は文化、時代とともに変化していきますので、辞書によっては「肯定的な使われ方をするようになってきた」という風に、プラスの意味合いを許容するものも出てきています。
ただ、特にご年配の方はこの「こだわり」「こだわる」という言葉について、本来の意味で認識をされている方がたくさんいらっしゃいます。商売はターゲットを決めて行うもの。なかでも、そういった方々を対象とされたようなお店で「素材にこだわりました!」なんて表現をしてしまうと、違和感を与えてしまう可能性もありますね。
「こだわる」のが難しいのであれば ~解決編
「こだわり」という言葉は、使う場面を間違えると逆の意味で伝わってしまう可能性がある。ならば、その言葉を置き換えてしまう方が無難かもしれません。
・厳選された
・選りすぐりの
・丹精込めて作った
・生産者の顔の見える
・想いをこめて育んだ
たとえばこれらの表現を用いれば、その料理なり素材なりの本来の魅力価値を伝えることが出来ますね。
言葉は変化するものですので、こだわりのないようでありたいものですが、誤解されて伝わってしまってもいけません。いま、「こだわり」が変遷のまっただ中にあるのだとすれば、置き換える表現を意識してみるのも一つの方法ですね。


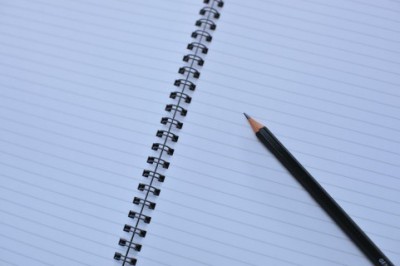




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
