始まりに「これをやるぞー」と目標を立てたものの、たいていは中途半端。
目標とは挫折を伴うものですが、省みても、目標の残骸らしきものがたくさんある我が人生だなぁと恥ずかしい気持ちになります(^^;
そんな自分にも、そんな自分だから、褒めてあげてもいいかなと思える過去の思い出たちがあります。
- 明石から姫路までの40キロをジョギングで走り終えたこと
- 魚の骨を上手に取りながら食べられるようになったこと
- 泣かずに歯医者さんに行けるようになったこと
目標を書き出すことは、とても大切。
また、過去の栄光にこだわりすぎることは執着となってしまい良くないこともあります。
それでも
自分の成し得てきたことを棚卸しして、自分の目次を作って強みの見える化を行うと、次の目標実現に向けてモチベーションになる。
こう考えて自分を認めてあげる時間も、作ってあげたいと思うのです。
ひとは、ひとに認められたい生き物。何よりも先ず、自分が自分を認められないで周囲に自分の声を届けていくことは出来ませんよね。
自分を好きでいるための、過去形。自分を許してあげることも、次の景色を望むためにはきっと大切なことなんですよね。
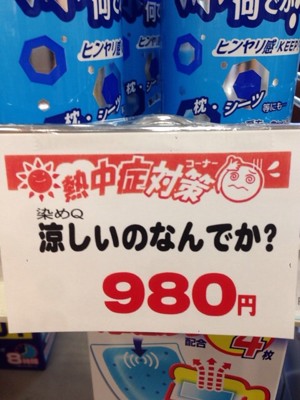
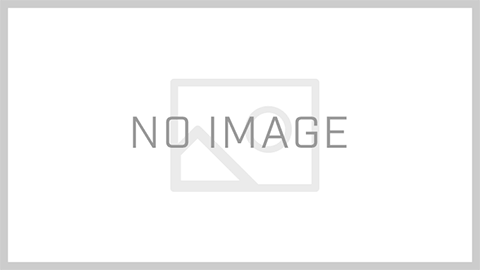

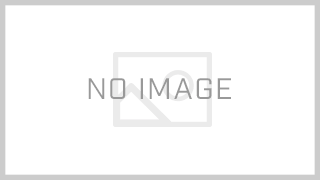
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
