以前「ご冥福をお祈りします」という言葉は安易に使ってはいけないという記事を書きましたが、人が亡くなることについては、その立場や信仰などにより、書き方に十分な注意をする必要があります。
今回は「往生」という言葉について「他界」とどう違うのか、まとめます。
「往生」と「他界」の意味の違いと使い分けについて

「往生」も「他界」も人が亡くなることに違いはないのですが、使い方には注意が必要です。
「往生」は仏教用語なので仏教徒の場合にのみ使える
「他界」は宗教信仰に関係なく使える言葉
「往生」は仏教用語なので仏教徒の死去に使う言葉になります。
景戒という人が「不幸の衆生は、必ず地獄に堕ち、父母に孝養すれば、浄土に往生す」と使ったのが(文書に残る上では)始まりと言われており、その後、源信が「応に苦海を離れ、浄土に往生すべし」と記して以後、広く使われるようになったという記録が残っています。
「浄土」という考え方は、今生きるこの世を去ったのちに訪れる場所であるという仏教の概念。ですから、仏教を信仰とする人以外の死去に伴って「往生」という言葉を使うと問題の生じる可能性があります。
「往生」に対して「他界」という言葉は、仏教と関係のない中国の書物に出典があります。
「他界」とは「ほかの世界」ということ。つまり、「他界」が示す「ほかの世界」とは「浄土」のことであるとは限らず、広い意味での死後の世界であると言えます。
往生が極楽を意味して、他界は一般的な死後の世界のことを指すということはつまり、キリスト教や神道など、仏教以外の「死後の世界」の概念に対しても広く使えることを意味しているわけです。故人の宗教や信仰が定かでない場合は、往生という言葉を用いることなく「他界」という言葉を使った方が無難であると覚えておくと間違いはないですね。
「死去」を表す言葉で注意しておきたいもの
死去を表す言葉の用い方にはいろいろと注意が必要です。
冒頭でもお伝えしたとおり「ご冥福をお祈りします」という言葉は安易に使わないということ、また、「逝去」という言葉は、どの立場の人が亡くなったかということを考えて使わなけければいけないということも以前ご紹介しました。
10秒で分かるご冥福を祈ってはいけない理由 ~御霊前と御仏前のその違い
浄土真宗は日本で一番大きな宗派。その葬儀御法要に参列するときに気を付けなければいけないことをご紹介しています。
「弊社社長が逝去いたしました」という言葉を使ってはいけない理由
逝去という言葉、他界という言葉の使い方について紹介しています。
そして、皇族の方が亡くなったときに用いる言葉もあるという記事も書きました。
皇族の方が逝去されたときに用いる「崩御」「薨御」「薨去」「卒去」について
皇族の方が亡くなったときに「逝去」という言葉を使ってもいいのかどうか。正しい言葉を用いることが、正しい事実を伝えるとは限らないその理由について紹介しています。
宗教や信仰は、いわば、その方の人格や個性を表すもの。憲法でも保障されている通り、最大限の敬意を払って尊重しなければなりません。
普通に生活している限りはあまり使うことのない言葉ですが、何かあったときには(そういえば色々と注意しなくちゃいけないんだったな……)程度には思い出して検索できるようにはしておきたいですね。




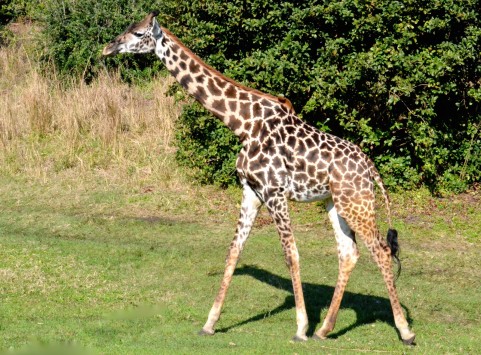

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
