自分のことを話すよりも相手に質問をして話をしてもらった方が会話が弾むのは皆さんもご存じだろうと思います。特に相手が年上や目上の方の場合は質問をすることが相手への最大のギフトと考えるようにしておくと有効的。相手から色々なことを教えてもらうという素直な態度で接したいものです。
今回は、年上や目上の方から何かを教えてもらうときに使う「ご教授ください」と「ご教示ください」の意味の違いと使い分けについて整理してみましょう。
「ご教授ください」と「ご教示ください」の意味の違いと使い分け

「ご教授ください」と「ご教示ください」はどちらも文法的には誤りではありません。
「ご教授ください」の「教授(=大学の教授)」という言葉からイメージを膨らませて、普通に会話をしている相手に「ご教授ください」と口頭で伝える機会はあまりない(大袈裟である)と覚えておくと良いでしょう。
「ご教授ください」で教わる内容は学問や芸術、高度な技術や技能。
「ご教示ください」は「教えてください」をより丁寧に言い換えたもの。
「ご教授ください」で授けられる内容は学問や芸事、技術や技能などです。
職人を目指して師匠に弟子入りするというときや、定期的に指導を受けることになるその最初の挨拶で使う場合はふさわしい表現であると言えるでしょう。また、教授される内容は教え方の手順が確立されているものと覚えておきます。「道」や「段階」「プロセス」といったようなものが教え授けられるもの、そのイメージが浮かんできますでしょうか。
それに対して「ご教示ください」は「教えてください」の言い換え表現。
一般的な会話では「ご教授ください」を使うことは滅多になく「ご教示ください」を使うと考えて良いでしょう。教授される内容が「道」や「段階」といったものであるのに対して、教示されるものは「ヒント」であると区別すればイメージが掴みやすくなりますね。
実際に声に出して「ご教授ください」という言葉の大袈裟な印象を覚えておく。そのうえで「ご教示ください」という言葉を何度か声に出して耳に馴染ませておけば、会話のときに自然に使えるようになると思います。
「教えを請う」と「教えを乞う」はどちらが正しい?
「教えを請う」と「教えを乞う」、この「請う/乞う」の違いについても以前紹介しています。

「請う」は自分がすることを許してほしいと願い、「乞う」は相手にしてほしいとお願いすることでした。「許可申請」という言葉で覚えておくと使い分けを間違えなくなるということについても紹介していますので、あわせて確認していただけると幸いです。


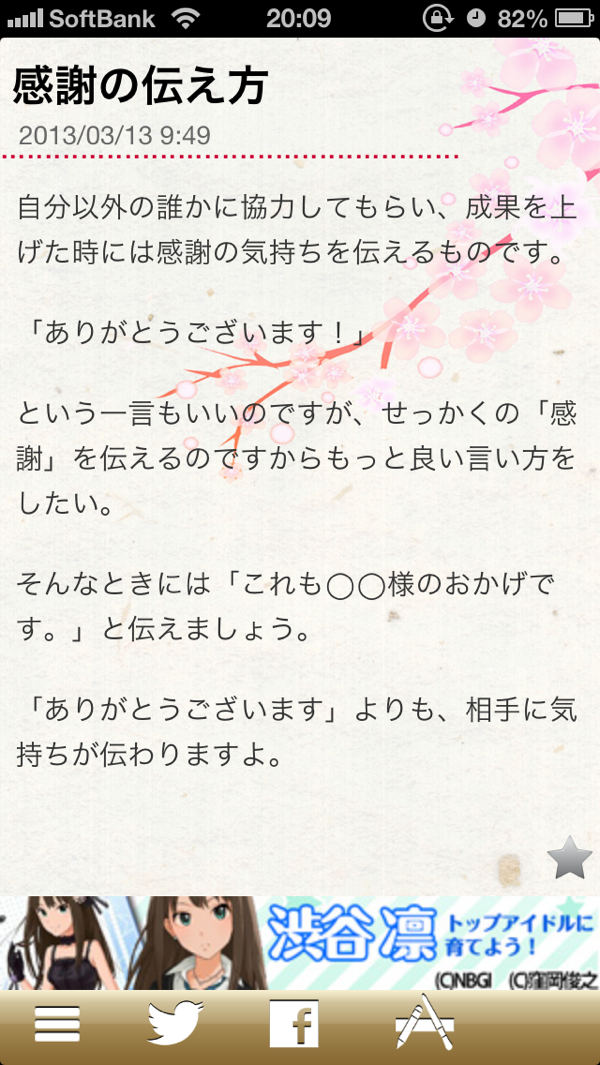



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
