「争いを避けて共存していく道を探る」というような表現のときに使われる、この「共存」という言葉。「きょうぞん」と変換しても表示されますが、共存は「きょうそん」と読むのが本来(ただし、最近では「きょうぞん」と読んでも間違いではないとしている辞書も増えてきています)。
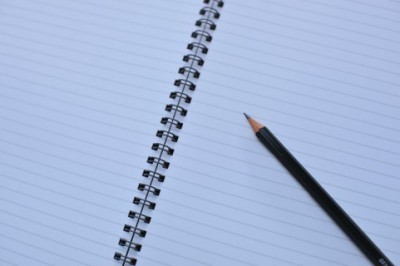
今回は、この「存」という字を「そん」と読むときと「ぞん」と読むときの区別の仕方についてまとめてみます。
共存は「きょうそん」と読むのが正しかった ~「存」を「そん」「ぞん」と読む区別の仕方
「存」という字が「そん」「ぞん」と読むことが出来るのはご承知の通り。では、音が濁るときと濁らないときの区別の仕方はどうすれば良いのでしょうか。
「存」を「そん」と読む漢字の例:
存在、残存、存否
併存、存立、依存
現存、存続、存亡
「存」を「ぞん」と読む漢字の例:
存念、異存、存ずる
存外、存知、存分
「存」という字の音が濁るものと濁らないものをまとめてみました。こうして漢字で並べてみると、音が濁る・濁らないの違いを感覚的にご理解いただけるかもしれませんね。「そん」と読む場合の漢字のグループは、対象となるものが目の前にあるイメージが出来ますが、「ぞん」と読む漢字のグループは、心の内面(think)にあることがわかります。
「考える」「思う」という心の内面を伝えるとき
「存」は「ぞん」と読む「ある」「いる」という具体的な存在を伝えるとき
「存」は「そん」と読む
ただし、実存・生存という漢字だけは例外的に「じつぞん」「せいぞん」と読むので注意してください。タイトルにした「共存」は、対象となるものが存在するので、このルールに基づいて「きょうそん」と読むことが正解となります。
現存・残存・併存・共存・依存の読み方は?
現存・残存・併存・共存・依存というこれらの漢字も本来は音が濁りません。ただ「げんぞん」「ざんぞん」という音の響きを聞いてもほとんどの人にとって違和感がないように、多くの解釈では濁って読んでもOKというルールになってきつつあります。今回お伝えしている「存」という字の読み方の区別はあくまでも原則、言葉は意味だけではなく、その読み方も変化しつつあるということを知るいい一例であると言えるのではないでしょうか。
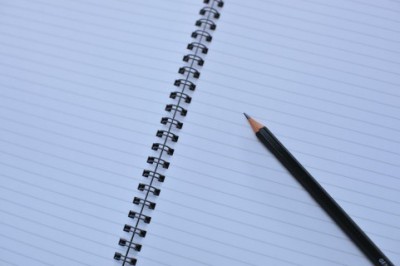
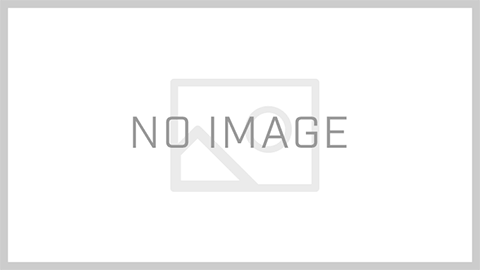
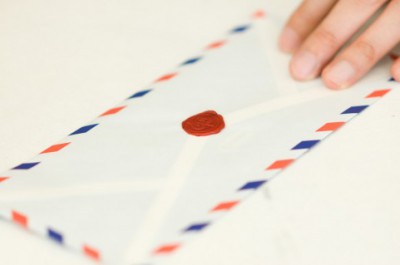
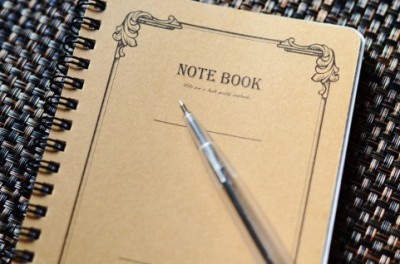


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
