「雨が降り出して、時を分かたず、彼は傘を持って飛び出して行った」
このように「時を分かたず」を「すぐに」という意味で使っている文章を見かけることがあります。「時を分かたず」の意味を「すぐに」と考えるのは誤用。今回はこの「時を分かたず」の意味について確認しておきましょう。
「時を分かたず」の意味は「すぐに」ではない

時を分けることなく、と考えると、時と時の間に空白がないイメージになってしまいますが「分かたず」は「区別がない」という意味であることを理解しておけば誤った使い方をしないようになります。
「時を分かたず」の意味は「いつも」
すぐにという意味で使うのは誤用
こんなときでもあんなときでも時を区別することがない。つまり「時を分かたず」の意味は「いつも」ということになります。
「事故のおきた交差点で、時を分かたず警察官が警戒を行っていた」という文章の場合は、事故の直後に警察官が立っていたということではなく、事故後いつその交差点を通りかかっても警察官立ち続けていたという状況を表します。
似た誤用の多い「おもむろに」「やおら」の意味も確認しておく
「おもむろに」「やたら」という言葉も「すぐに」「急に」という意味で誤用されることが多い言葉。

iPhoneやパソコンの変換機能で試してみるとすぐに意味がわかりますと紹介した以前の記事へのリンクはこちらになりますので、あわせてご確認ください。「おもむろに立ち上がった」「やおら、振り向いて彼は言った」という表現は、さて、どんな意味だったでしょうか。
文化庁の国語に関する世論調査では
平成20年に行われた文化庁の国語に関する世論調査では、「時を分かたず」を7割近くの人が誤用の「すぐに」という意味で理解していることがわかりました。

「時を分かたず」の意味を問われて、正しい意味である「いつも」と回答した人は1割強。この状況を考えると、今後ますます誤用の意味が一般化していく傾向にあると言えそうですが、今の段階ではまだ、この使い方は誤用であるとされています。口語ではあまり使うことのない表現かもしれませんが、文章の格調を高めるときに使われる機会も多くありそう。自分が正しい意味を理解していたとしても、多くの読み手は意味を誤解する可能性があるということは覚えておくほうが良いかもしれませんね。

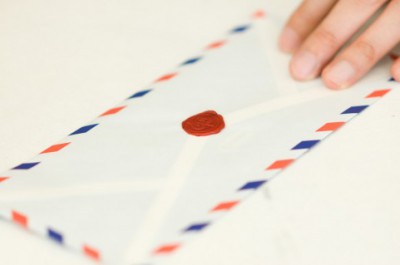




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
